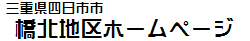橋北地区の成り立ち
橋北地区は、中心市街地の北に位置し、海蔵川と三滝川に挟まれ、
古くは地区を通る東海道沿いに栄え、当時は四日市の文化や生活の中心となった地区です。
橋北地区の歴史は明治22年(1889)年、三重郡浜一色村が四日市町となったのがはじまりで、
明治29(1896)年に四日市商業学校(現四日市商業高等学校)が創立されました。
その後大正5(1916)年に第七尋常小学校(現西橋北小学校)が、昭和11(1936)年に第八尋常小学校(現東橋北小学校)が創立されました。
昭和22(1947)年には商業学校跡地に橋北中学校も創立されました。現在橋北地区には創立当初と同位置に小・中学校3校があり、子どもたちが元気に通っています。
陶栄町の「萬古焼き」は市の地場産業の一つとなっています。毎年、5月の第2土日には、「四日市万古まつり」が開催され、
「ばんこの里会館」をはじめ数多くの店が立ち並び、それを目当てに全国からたくさんの人が集まります。
昭和30年以降、午起地区の沿岸部が埋め立てられて、大協石油(現コスモ石油)午起製油所、大協和石油化学、協和油化、中部電力四日市火力発電所とで、第2コンビナートが形成され、現在に至っています。